エア下僕のねこ部屋
いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場
今日からお口編。
基本的な構造はどの猫も変わらないが、個体や品種によって大きさ(口の端がどの位置まであるかとか縦横比とか)はけっこう変わる。
歯の並び(噛み合わせ)が水平に近いのに対し、口(唇)の形は三次元的な構造になっていて、ヒトのそれとはかなり異なっている。唇はヒトのような器用な動かし方は出来ない。


ずいぶん以前から抱えている問題であるが、猫を描こうとする時、輪郭線の方向と毛の生えている方向との相反性に悩まされる。輪郭に沿って線を引けば、それはモフモフな猫ではなく肉の塊になってしまう。と言って、輪郭線とは角度を変えて毛を表現すると、その部分(輪郭線沿い)だけがリアルになって何となく不自然になる。輪郭の内側にも毛の表現が必要になるのである。(そもそも猫の輪郭線とはどの部分を指すのか?地肌なのか毛の平均的な中央辺りなのか眼で見えなくなる毛の先端辺りなのか?)
思い切って単純化(デフォルメ)するならともかく、中途半端に毛並みの表現を入れるとかえって何が描かれているのかわからなくなることがある。きちんと理解してもらえるだけの情報量を描きこもうとすればその分、時間はかかることになる。
以前にも書いたような気がするが、自分は猫だとわかりさえすればいい絵を描きたいわけではなくて、モフモフな猫が描きたいのである。究極を言えば、思わず手を伸ばしてナデナデしたくなるような質感(ひいては生命感)をも表現したい。そのための前提として、リアルさにこだわらないわけにはいかない。
しかし、ひとつの作品にやたら時間をかけていては、猫の持つ様々な表情や変幻自在な魅力を表現し切れないのではないかとも思う。
質感表現(情報量のレベル)と時間的工数的な兼ね合いは、ちょっと考えておいたほうがいいかも知れない。
基本的な構造はどの猫も変わらないが、個体や品種によって大きさ(口の端がどの位置まであるかとか縦横比とか)はけっこう変わる。
歯の並び(噛み合わせ)が水平に近いのに対し、口(唇)の形は三次元的な構造になっていて、ヒトのそれとはかなり異なっている。唇はヒトのような器用な動かし方は出来ない。
ずいぶん以前から抱えている問題であるが、猫を描こうとする時、輪郭線の方向と毛の生えている方向との相反性に悩まされる。輪郭に沿って線を引けば、それはモフモフな猫ではなく肉の塊になってしまう。と言って、輪郭線とは角度を変えて毛を表現すると、その部分(輪郭線沿い)だけがリアルになって何となく不自然になる。輪郭の内側にも毛の表現が必要になるのである。(そもそも猫の輪郭線とはどの部分を指すのか?地肌なのか毛の平均的な中央辺りなのか眼で見えなくなる毛の先端辺りなのか?)
思い切って単純化(デフォルメ)するならともかく、中途半端に毛並みの表現を入れるとかえって何が描かれているのかわからなくなることがある。きちんと理解してもらえるだけの情報量を描きこもうとすればその分、時間はかかることになる。
以前にも書いたような気がするが、自分は猫だとわかりさえすればいい絵を描きたいわけではなくて、モフモフな猫が描きたいのである。究極を言えば、思わず手を伸ばしてナデナデしたくなるような質感(ひいては生命感)をも表現したい。そのための前提として、リアルさにこだわらないわけにはいかない。
しかし、ひとつの作品にやたら時間をかけていては、猫の持つ様々な表情や変幻自在な魅力を表現し切れないのではないかとも思う。
質感表現(情報量のレベル)と時間的工数的な兼ね合いは、ちょっと考えておいたほうがいいかも知れない。
PR
鼻練習はここいらで終了。
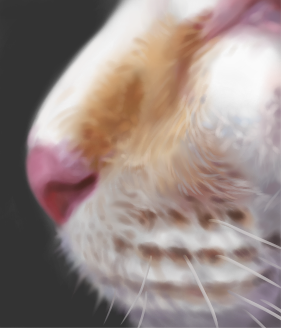

Fire Alpacaには様々なブラシが用意されていて、それぞれを自分でカスタマイズすることも出来るし、ビットマップ画像を自分で用意してオリジナルブラシを作ることも出来る。とは言え、あまりそうしたブラシ機能に頼っていては実力がつかないのではと思い、なるべく使うブラシの種類を抑えるようにしていた。
メインで使っているのは水彩ブラシで、補助的に指先ブラシ、エアブラシ、鉛筆ツールである。エアブラシは使わないことも多く、背景を描く場合はビットマップブラシを使うこともある。
しかし、質と量(スピード)を両立したいのなら、ブラシ機能に頼るのもひとつの選択肢としてアリなのではとも思い、以前作成した刷毛ふうのビットマップブラシを併用してみることにした。

結果はと言えば、質感はこれまでと異なる感じにはなったが、制作時間はさほど変わらずであった。
パーツごとのディテールを究めたいのであればざっくりした仕上がりで良いわけはなく、ディテールを描き込めば否応なく時間はかかる。今やってる練習のテーマを考えれば、スピードを気にかけるより猫のディテールのありようを理解し覚えることを優先すべきかなとも思う。
各パーツの練習が一巡するまでは、じっくり腰を据えて取り組むしかあるまい。
Fire Alpacaには様々なブラシが用意されていて、それぞれを自分でカスタマイズすることも出来るし、ビットマップ画像を自分で用意してオリジナルブラシを作ることも出来る。とは言え、あまりそうしたブラシ機能に頼っていては実力がつかないのではと思い、なるべく使うブラシの種類を抑えるようにしていた。
メインで使っているのは水彩ブラシで、補助的に指先ブラシ、エアブラシ、鉛筆ツールである。エアブラシは使わないことも多く、背景を描く場合はビットマップブラシを使うこともある。
しかし、質と量(スピード)を両立したいのなら、ブラシ機能に頼るのもひとつの選択肢としてアリなのではとも思い、以前作成した刷毛ふうのビットマップブラシを併用してみることにした。
結果はと言えば、質感はこれまでと異なる感じにはなったが、制作時間はさほど変わらずであった。
パーツごとのディテールを究めたいのであればざっくりした仕上がりで良いわけはなく、ディテールを描き込めば否応なく時間はかかる。今やってる練習のテーマを考えれば、スピードを気にかけるより猫のディテールのありようを理解し覚えることを優先すべきかなとも思う。
各パーツの練習が一巡するまでは、じっくり腰を据えて取り組むしかあるまい。
パーツごとのディテールの練習途中であるが、夏も終わりそうなので、以前から気になっていたことについて徒然に考えてみたいと思う。
なぜ急にそんなことを言い出したかと言うと、タイトルのごとく「猫の鼻の横のスリットは何のためにあるのか?」という疑問の答えについて、ヒントが手に入った気がするからである。
そのヒントとは、この画像(その模写)である。↓

おわかりいただけただろうか?
そう、スリットタイプの鼻の穴は、手指などを使わずに開閉することが出来るのである!
ヒトのような丸っこい形の鼻の穴より、スリット型の穴のほうが効率的確実に開閉可能なのは言うまでもないと思う。
とは言え、まだ疑問は完全に払拭されたわけではない。確かに、水中生活が多いアザラシやアシカなどの海獣類、あるいはホッキョクグマやカバ、はたまた砂漠のような特殊な環境に住むラクダ(砂が入るのを防ぐためと言われる)など一部の哺乳類は鼻の穴を開閉出来るが、スリットタイプの鼻を持つ多くの動物は、実際には鼻の穴を自由に閉じることは出来ないと思われる。少なくとも、スリット型の鼻穴であればどんな動物も開閉出来ますよと言うようなソースは、ざっとネットで調べてみた限りでは見当たらなかった。
イエネコの場合、シャーッと威嚇した時とかあくびをした時は鼻の穴は閉じてしまうように見える。しかしイエネコが水に濡れることを嫌うのは有名な話で、水中に入ることを想定して開閉機能を備えたとは考え難い。かと言って、威嚇やあくびのためにどうしても鼻の穴を閉じる必要があったとも思えない。
これらは顔面の構造や機能上、たまたま鼻の穴も閉じてしまう結果になっただけと考えたほうが自然な気がする。
トラのような水中に入ることを厭わないネコ科動物は例外的な存在だ。
多くの陸生哺乳類にとっては水中にどっぷり浸かって生活する必要はなく、従って開閉可能な鼻の穴の必然性はまずないのである。
厳密に数えてみたわけではないが、スリットノーズを持つ哺乳類は、そうでない哺乳類よりずっと種類が多いように思える。その多くが鼻の穴を開閉出来ない(する必要がない)のなら、彼らはなぜスリットノーズを持っているのだろうか?
ここから先は、特にソースのない単なる想像である。
地球上に現れた最初期の哺乳類は、ネズミのような小さな生き物だったそうである。
当時はまだ爬虫類その他の天敵に対抗し得る体機能もなく頻繁に狙われただろうし、襲われたら逃げ回るしかなかっただろう。その頃の哺乳類は基本的には陸生であったのだろうが、陸上のみならず水中でも移動、活動が可能であれば生き延びられる確率は格段に上がったはずである。
だから彼らは鼻の穴をスリット型にして、開閉可能なように進化した。初期の哺乳類は水陸両用型であったわけだ。
原始的な哺乳類の鼻が本当はどんな構造だったのかはわからないし、水陸両生だったという証拠もないが、この考え方は、元来陸生であったはずの哺乳類の中からクジラやイルカのような完全に水中生活に適応した種がなぜ派生したのかもうまく説明出来る気がする。共通の祖先が水陸両用タイプだったのであれば、後に水中生活を専門に選択した種が現れたとしてもさほど不思議ではない。
やがて種の分化が進み哺乳類のバリエーションが増え、しかも爬虫類全盛の時代が終わると、鼻の穴を閉じなくても困らない生活条件で暮らす種も増えた。ヒトの瞬膜がそうであるように、「使わない」機能はやがて「使えない」機能になるのである。
使わない器官は退化するものであるが、開閉機能が失われたにもかかわらず、鼻の穴のスリットが消失することなく多くの哺乳類の鼻に残されているのはなぜなのか?
それは単なる祖先の名残り、「使わないけど、この形でも別に困らないから放っておくか」と言うぐらいのことではないだろうか。開閉機能は失われても鼻そのものは必要な器官であったから、消失する方向には退化しなかったのである。
身体構造の進化的な変化は、「このままだとヤヴァいマジで!」ぐらいに切羽詰まらないと起きないのではないかと思う。
スリットノーズでない哺乳類の種類が少ないのは、そういう面倒な事情を抱えてしまった種が少なかっただけのことであろう。全部の事情まではわからないが、例えばゾウは、ああいう鼻の使い方をするのならスリットノーズにこだわるわけにはいかなかったろうなと推測出来る。
では、ヒトはなぜスリットノーズを捨てたのだろうか?そこまで切羽詰まった事情とは何であったのか?
まあ、そのあたりはどうでもいい話である。
なぜ急にそんなことを言い出したかと言うと、タイトルのごとく「猫の鼻の横のスリットは何のためにあるのか?」という疑問の答えについて、ヒントが手に入った気がするからである。
そのヒントとは、この画像(その模写)である。↓
おわかりいただけただろうか?
そう、スリットタイプの鼻の穴は、手指などを使わずに開閉することが出来るのである!
ヒトのような丸っこい形の鼻の穴より、スリット型の穴のほうが効率的確実に開閉可能なのは言うまでもないと思う。
とは言え、まだ疑問は完全に払拭されたわけではない。確かに、水中生活が多いアザラシやアシカなどの海獣類、あるいはホッキョクグマやカバ、はたまた砂漠のような特殊な環境に住むラクダ(砂が入るのを防ぐためと言われる)など一部の哺乳類は鼻の穴を開閉出来るが、スリットタイプの鼻を持つ多くの動物は、実際には鼻の穴を自由に閉じることは出来ないと思われる。少なくとも、スリット型の鼻穴であればどんな動物も開閉出来ますよと言うようなソースは、ざっとネットで調べてみた限りでは見当たらなかった。
イエネコの場合、シャーッと威嚇した時とかあくびをした時は鼻の穴は閉じてしまうように見える。しかしイエネコが水に濡れることを嫌うのは有名な話で、水中に入ることを想定して開閉機能を備えたとは考え難い。かと言って、威嚇やあくびのためにどうしても鼻の穴を閉じる必要があったとも思えない。
これらは顔面の構造や機能上、たまたま鼻の穴も閉じてしまう結果になっただけと考えたほうが自然な気がする。
トラのような水中に入ることを厭わないネコ科動物は例外的な存在だ。
多くの陸生哺乳類にとっては水中にどっぷり浸かって生活する必要はなく、従って開閉可能な鼻の穴の必然性はまずないのである。
厳密に数えてみたわけではないが、スリットノーズを持つ哺乳類は、そうでない哺乳類よりずっと種類が多いように思える。その多くが鼻の穴を開閉出来ない(する必要がない)のなら、彼らはなぜスリットノーズを持っているのだろうか?
ここから先は、特にソースのない単なる想像である。
地球上に現れた最初期の哺乳類は、ネズミのような小さな生き物だったそうである。
当時はまだ爬虫類その他の天敵に対抗し得る体機能もなく頻繁に狙われただろうし、襲われたら逃げ回るしかなかっただろう。その頃の哺乳類は基本的には陸生であったのだろうが、陸上のみならず水中でも移動、活動が可能であれば生き延びられる確率は格段に上がったはずである。
だから彼らは鼻の穴をスリット型にして、開閉可能なように進化した。初期の哺乳類は水陸両用型であったわけだ。
原始的な哺乳類の鼻が本当はどんな構造だったのかはわからないし、水陸両生だったという証拠もないが、この考え方は、元来陸生であったはずの哺乳類の中からクジラやイルカのような完全に水中生活に適応した種がなぜ派生したのかもうまく説明出来る気がする。共通の祖先が水陸両用タイプだったのであれば、後に水中生活を専門に選択した種が現れたとしてもさほど不思議ではない。
やがて種の分化が進み哺乳類のバリエーションが増え、しかも爬虫類全盛の時代が終わると、鼻の穴を閉じなくても困らない生活条件で暮らす種も増えた。ヒトの瞬膜がそうであるように、「使わない」機能はやがて「使えない」機能になるのである。
使わない器官は退化するものであるが、開閉機能が失われたにもかかわらず、鼻の穴のスリットが消失することなく多くの哺乳類の鼻に残されているのはなぜなのか?
それは単なる祖先の名残り、「使わないけど、この形でも別に困らないから放っておくか」と言うぐらいのことではないだろうか。開閉機能は失われても鼻そのものは必要な器官であったから、消失する方向には退化しなかったのである。
身体構造の進化的な変化は、「このままだとヤヴァいマジで!」ぐらいに切羽詰まらないと起きないのではないかと思う。
スリットノーズでない哺乳類の種類が少ないのは、そういう面倒な事情を抱えてしまった種が少なかっただけのことであろう。全部の事情まではわからないが、例えばゾウは、ああいう鼻の使い方をするのならスリットノーズにこだわるわけにはいかなかったろうなと推測出来る。
では、ヒトはなぜスリットノーズを捨てたのだろうか?そこまで切羽詰まった事情とは何であったのか?
まあ、そのあたりはどうでもいい話である。
今回からお鼻編に入ろうと思ったのだけれど、なんか急に腰が痛くなってしまった(わりとマジなやつ)ので、1枚だけ。

猫の鼻は左右外側にスリット(切れ目)があるが、見えてる穴から少し奥に入ると鼻腔への入り口はかなり狭くなっている。おそらくこの構造で異物の吸引を防いでいるのだろう。
少なくとも鼻の穴から鼻毛が飛び出している猫の画像を見たことはない。
この鼻の横のスリットは他の動物にも見られるが、スリットがある動物とない動物との分類上の共通点がよくわからない。他のネコ科の動物にもスリットはあるが、ウシやウマ、シカなどにもそれに近い構造があるので、肉食か草食かの違いではない。草食でも例えばゾウにはこうしたスリットはない。
雑食性のクマにはスリットがあるが、ブタにはない。チンパンジーやニホンザルにはそれらしき構造が見られるが、ゴリラにはスリットと言えるようなレベルの構造はない。
生息環境、あるいは鼻や口周りを使う動作(例えば食事)上の共通点で考えてみるのもちょっと難しそうである。今のところ全く答えの見当がつかない。
まあ別にどうでもいいんだけど。
猫の鼻は左右外側にスリット(切れ目)があるが、見えてる穴から少し奥に入ると鼻腔への入り口はかなり狭くなっている。おそらくこの構造で異物の吸引を防いでいるのだろう。
少なくとも鼻の穴から鼻毛が飛び出している猫の画像を見たことはない。
この鼻の横のスリットは他の動物にも見られるが、スリットがある動物とない動物との分類上の共通点がよくわからない。他のネコ科の動物にもスリットはあるが、ウシやウマ、シカなどにもそれに近い構造があるので、肉食か草食かの違いではない。草食でも例えばゾウにはこうしたスリットはない。
雑食性のクマにはスリットがあるが、ブタにはない。チンパンジーやニホンザルにはそれらしき構造が見られるが、ゴリラにはスリットと言えるようなレベルの構造はない。
生息環境、あるいは鼻や口周りを使う動作(例えば食事)上の共通点で考えてみるのもちょっと難しそうである。今のところ全く答えの見当がつかない。
まあ別にどうでもいいんだけど。
プロフィール
最新記事
(04/28)
(04/21)
(04/15)
(04/09)
(03/25)
アーカイブ
ブログ内検索
忍者カウンター
P R

